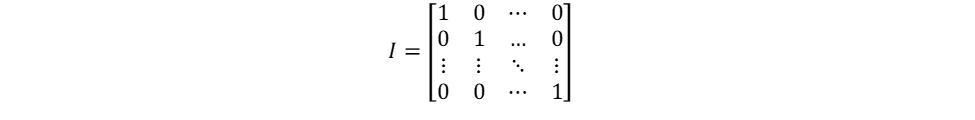本ページでは、パレート効率的とはどのような状態をいうのかについてまとめたい。
資源配分の効率性についての言葉であるが、一言でいえば「他のどの人の効用も下げることなく、誰かの効用を上げることができない資源配分の状態」ということができる。逆に、「他のどの人の効用も下げずに誰かの効用を上げることができる」ことをパレート改善という。
a,b,cという3 通りの配分を考えてみる。そして、個人1、個人2という2人の個人が存在しているとする。
それぞれの配分における個人1、個人2の効用は、
a=(10,15)
b=(11,15)
c=(0,20)
であるとする。
このとき、cの配分はパレート効率的だが(aまたはbに変更しようとすると個人2の効用が必ず下がるので)、個人1にとっては最悪の配分となってしまう。
aの配分については、bに変更する事で、個人2の効用を下げる事なく、個人1の効用を上げることができる。その意味で、aはパレート効率的ではない。配分bは、パレート効率的となる。
よって、この例においてパレート効率的なのはbとcということになる。
この例から何が分かるだろうか。
現状パレート効率的でない配分 (上記の例でいえばa) となっている場合、資源配分を調節することにより、他の誰の効用も損なわずに一部の個人の効用を向上させることができる(上記のb)。
では、パレート効率的な状態が必ず最善の状態かと言えば、必ずしもそうではない。
上記の例では、cの配分もパレート効率的であるが、個人2の効用が20であるのに対して個人1の効用はゼロである。ここに、絶対的な"不平等"が存在している。
このように、パレート効率的な配分は、誰の効用も下げることなく誰かの効用を上げることができないという効率性を満たしたものであるだけで、その配分の平等性については何も語っていない。一般的に、パレート効率的であっても、大多数の個人にとっては極めて不公平であり、望ましくないと考えられる配分は存在しうる。政策によりパレート効率的になるよう誘導したとしても、その結果不平等が加速することも考えられる。効率性と平等性は分けて考えなければならない。
完全競争市場(市場に多数の消費者と生産者が存在し、個々の経済主体は価格への影響力を一切持たない、つまりプライステイカーとなる市場)における均衡点で達成された資源配分はパレート効率的である(厚生経済学の第1基本定理)。
(参考):
Kaushik Basu(2011)"Beyond the Invisible Hand: Groundwork For A New Economics"